10/25(木)日本橋で日本映画を観よう『裸の島』の上映後、新藤次郎さん(協同組合日本映画製作者協会・理事長/映画プロデューサー)、大河内直之さん(東京大学先端科学技術研究センター・特任研究員)、古川康さん(第12回全国障害者芸術・文化祭実行委員会会長/佐賀県知事)が登壇、シンポジウム『バリアフリー映画をスタンダードに』が行われました。
司会はMASC/虹とねいろプロジェクトの松田高加子さんです。

新藤次郎(以下、新藤):私の父である新藤兼人自身が一番好きで、世間的にも代表作というのが今ご覧になった『裸の島』です。観ていただいた通り台詞がひとつもない。映像で淡々と乾いた土に水を掛ける、というような映画です。会社がもう倒産するというときに新藤兼人は、“最後にこの映画を1本撮って解散しよう”と思って撮ったそうです。父には映画というのは映像たらしめたいという思いが根っからあって、最後だからとそれを純粋にやった。しかし、映画のバリアフリー化で、『裸の島』をやりたいと聞いたときは正直“エッ!?”と思いましたね。台詞のないこの映画をバリアフリー化して、どれだけ実験的な試みを感じることができるか心配でした。音声のミキシングをもう一歩というか、ちょっとナレーションの音が大きいかなということはありましたが、私自身は心から十分に楽しめました。
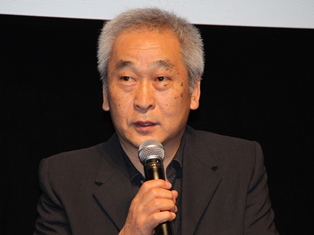
古川康(以下、古川):私は副音声が付くことで、かえって映画が雄弁になったのではないかと思いました。副音声が付くほうがかえって、高いレベルで楽しめるのではないかという気がします。アッバス・キアロスタミの映画にも似た乾いた風景を補うような、それなりの音声解説が加えられることで、観ながら非常に助けにもなりました。私が知事を務めております佐賀県では、全国で最も大がかりな「バリアフリーさが映画祭」というのをやっております。バリアフリー映画に来ていただく一定数は高齢者です。彼らのなかから、今のテンポの速い映画を字幕なしで観るのは難しいという声もよくいただいていて、その意味で、こうした字幕とか副音声のある映画がもっともっと広がっていけばいいと思いました。

大河内直之(以下、大河内):東京大学の先端科学技術研究センターというところで10年前にバリアフリーを中心に研究する拠点ができて、私は今そこで研究員をしています。今回バリアフリー化された新藤兼人監督の『裸の島』を観て感じたのは、場面展開だったり、表情だったり、アングルだったりがとてもよく分かるということでした。台詞のない映画に可能性がないと思ってはいけないと強く感じましたね。新藤次郎さんも指摘されていたように、新しい副音声の音に映画の古い音というのがミスマッチで、私もその差を近づけることによって、もっと映画そのものに寄り添った副音声解説の音になるのかなと感じました。

司会・松田高加子:障害者の方向けの映画の見方には、副音声だけイヤホンで聴くという方法もありますよね。先生ご自身はどちらの方法がよいと思いますか。

大河内:もちろん、イヤホンで聴きながら映画を観るという方法もあってよいと思いますが、私は、より本編に馴染んでいる可能性も同時に追求したいと思います。副音声もみんなで聞いてみるという方法も、新しくて面白そうだなと。ひとりだけで副音声を聞くのもちょっと寂しいなと。みんなで新しいメディアを共有してみるというバリアフリーも追求したいというのが、今の仕事をするうえでの私のモチベーションとなっています。
古川:私も新しいメディアをみんなで共有してみるという考え方については、全く同感ですね。今、テレビは字幕がほぼ義務化されましたし、映画でも東宝が自分のところで作っている映画には、全部字幕を付けるということを決めたらしい。そういう意味で今後、字幕化は進んでいくだろうと思います。ただ残念ながら、映画についてはまだまだテレビほど進んでいません。少なくとも文部省のお金が出ている映画については、バリアフリー版を義務付けるということをやってくれないかと、今、文化庁に話しているところです。実際、厚生労働省には随分理解が広まっている。けれど、映画そのものを管理監督所管している文化庁は、まだまだというのが実感です。
新藤:私はプロデューサーとして映画を作っている者ですが、正直に申しますと、製作者側としてはまず、障害者に観ていただく前提では映画を作っていないですね。ところが、東京大学先端科学美術研究センターが、4年くらい前から行っているバリアフリーの映画の研究会に参加させていただいたときに、障害者の人も、劇場でみんなと一緒に新作を楽しみたいという意見があることを初めて知ったわけです。障害のある人に見せたい映画を観たいというわけではなくて、エロチックなものも危ないものも含めて、色々な映画を観たいという。それは衝撃的な意見であったわけです。それから、私自身も色々考えるようになったんですけど、では、いざ自分が障害者を考慮して編集なりミキシングなりをするかというとそうではないと思う。それは、私が障害者がどう映画を楽しむか、どのように楽しめていないかイメージすらできていない。ですから、ここに私が出席するのが適当かどうかさえ分からないのですが。けれど今後、映画をこういうバリアフリー上映会のような公開の場で楽しめるかどうか、私たち製作者も考えなきゃいけないし、答えがほしい。答えがあれば映画を作ってる人も、公開している人も――この人たちは商売人なわけですからお客さんが来れば作るわけで――バリアフリー用映画を作り始めるのではないでしょうか。古川知事も、文化庁の話を仰っていましたが、バリアフリー版を作れば予算がかかるわけです。その予算が別途で出れば、プロデューサーとしては作ってみようかということはあります。

大河内:映画というのが、障害者の人たちを全く考慮しないで作られているということなんですけど、映画でもドラマでも、好きだったら障害があろうがなかろうが皆さん観るわけです。実際、障害者の皆さんはバリアフリー化されていない映画を観ているわけです。ちょっと声が聞こえないシーンがあったら、見える人に電話で「あれはキスシーンなの?」と聞いたりして、足らない情報を補ったりしてる。そこに、あともう一押し二押ししてやれば映画のバリアフリー化ができるのではないでしょうか。たとえば、劇場で手の空いてる人が、障害者の人を駅まで迎えに行ける映画館があれば、見に行こうかとなるわけです。そうなれば、それだけ客が増えるはずなんです。そのあと、一押しがバリアフリー化なんだと、製作者側の人にも分かってもらえればと思います。
古川:全く仰る通りだと思います。今年の6月に韓国のヨスというところで万博が開かれたのですが、その日本館の行事として、佐賀県は、韓国のバリアフリーユニバーサルデザインを考えるという内容のシンポジウムを主催し、バリアフリー映像化された『ドラえもん』を世界初公開しました。総勢百数十人の視覚障害や聴覚障害のお客さんに来てもらって感想を聞いたら、「最後のタンポポが風に揺れているシーンが良かったです」と言う方がいた。それを聞いて、シーンという言葉の意味が我々と違う感じでもクッキリと浮かび上がっているんだろうという気がしました。私はこうした上映は世界的にも共鳴してもらえると思いますね。
新藤:確かに、映画というメディアは、観客の感情に直接訴えられるという凄い武器を持っています。文化の違う国の人に見てもらうのはもちろん、いつも普通に映画が楽しめない人に見てもらうというのも、また映画の勲章かと思いますね。私ははじめに、『裸の島』が近代映画協会最後の作品として作られたと言いましたが、蓋を開けてみたら、会社が再生するきっかけになった。モスクワ国際映画祭でグランプリを獲ってその場で60数か国から買い手が付いたんです。実験的な映画は商売にならないと思っていたのが、世界中に受け入れてもらえたんです。それを考えると、映画のバリアフリー化の事業化は、もしかしたら難しいことではないのかもしれない。障害者の方たちも、商売人である我々のほうに意見をダイレクトに届けて欲しいですね。県知事が動いているのですから、あとは商売人を動かせばいいだけなんです。


















 Check
Check






![「アジア映画の森-新世界の映画地図」(作品社)刊行記念 特集 アジア映画の森 2012年10/2(火) - 10/13(土)[日曜・月曜休館/10日間] 会場:アテネ・フランセ文化センター(御茶ノ水)](/ja/home/ban/jpg/bnr_asiawood.jpg)
![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)

